2016年08月19日
緑のカーテンing その2 カーテンを食べる
7月25日にご紹介した緑のカーテンはすくすくと成長中。
ゴーヤも、あちらに一つ、こちらに一つと実りはじめたので、これは食べねば。
あいにく、我が家でゴーヤを食するのは自分一人。
だったら、好き勝手に存分に料理を試せる。
今回、緑のカーテンにゴーヤを入れた時からやってみたかったことが2つ。
1.極若ゴーヤを食べる。
2.完熟ゴーヤを食べる。
まず極若ゴーヤはその若さゆえに苦みが少ないのではないかと思い、身の丈3cmほどのを生で食べてみた。
で、「栴檀は双葉より芳し」ではないが「ゴーヤはちびっこでも苦し」。
写真手前の2つがオープンサンドのゴーヤ載せ。

奥の2つは、トマトときゅうり。一緒に写真撮るとわかりにくいな。
バターを塗ったパンに、ゴーヤだけとゴーヤ+トマト。
ゴーヤだけだと、さすがに苦い。
プラストマトにすると、苦みがアクセントになって、かなりいい感じ。
写真にはないが、チーズをトッピングしてみたら、とてもいい感じになった。
ハムやサラミなどと合わせてもいいかもしれない。
パンは以前にご紹介した学園西町のブーランジェリー ア プッチ ヴーさまのくるみ食パン。
ご紹介記事はこちら。
そして、2番目の完熟ゴーヤを食べるは、結論から申しますと、今現在では失敗。
完熟ゴーヤではないのだが、完熟ゴーヤの種を、ずいぶん昔、新宿にあった奄美大島料理のお店でいただいたことがある。
完熟すると、種の周りのわたがえんじ色になるので、それを食べて、種は出すという、あけびのような食べ方。
これが、甘くてジューシーでトロピカルフルーツのようなおいしさ。
よしっ!ここはひとつ、完熟させねば!と実を一つ、ほったらかしにしていた。
色も明るいオレンジ色になり「そろそろかなー、そろそろかなー」と心待ちにしていたら・・・・・
腐ってしまった(涙)。
種だけは取りおいているので、来年はこの種から苗を育ててみようかな。
なお、下の一皿は、別のゴーヤで作った茄子入りゴーヤチャンプルー。
味付けには味噌を使う。
これは、前出の奄美大島料理のお店で教えていただいた。
奄美大島風のチャンプルーの特徴だとか。
なお、自分で作るときは、種やわたも実ごと輪切りにしてチャンプルーにしている。
種やわたも栄養が豊富らしいので。
そして何よりも、実を縦半分に切り、スプーンで種をかき出して、水でさらして、水分をふきとってって、栄養が逃げていきそうなうえに、め・ん・ど・う。
実ごと炒めると、種のカリカリの触感が、また楽しい。

今年の残暑は、とにかくやる気がありすぎる気がする。
夏バテに効果があると言われるゴーヤ。
さて、お次はどの実をおいしくいただこうかな?
ゴーヤも、あちらに一つ、こちらに一つと実りはじめたので、これは食べねば。
あいにく、我が家でゴーヤを食するのは自分一人。
だったら、好き勝手に存分に料理を試せる。
今回、緑のカーテンにゴーヤを入れた時からやってみたかったことが2つ。
1.極若ゴーヤを食べる。
2.完熟ゴーヤを食べる。
まず極若ゴーヤはその若さゆえに苦みが少ないのではないかと思い、身の丈3cmほどのを生で食べてみた。
で、「栴檀は双葉より芳し」ではないが「ゴーヤはちびっこでも苦し」。
写真手前の2つがオープンサンドのゴーヤ載せ。

奥の2つは、トマトときゅうり。一緒に写真撮るとわかりにくいな。
バターを塗ったパンに、ゴーヤだけとゴーヤ+トマト。
ゴーヤだけだと、さすがに苦い。
プラストマトにすると、苦みがアクセントになって、かなりいい感じ。
写真にはないが、チーズをトッピングしてみたら、とてもいい感じになった。
ハムやサラミなどと合わせてもいいかもしれない。
パンは以前にご紹介した学園西町のブーランジェリー ア プッチ ヴーさまのくるみ食パン。
ご紹介記事はこちら。
そして、2番目の完熟ゴーヤを食べるは、結論から申しますと、今現在では失敗。
完熟ゴーヤではないのだが、完熟ゴーヤの種を、ずいぶん昔、新宿にあった奄美大島料理のお店でいただいたことがある。
完熟すると、種の周りのわたがえんじ色になるので、それを食べて、種は出すという、あけびのような食べ方。
これが、甘くてジューシーでトロピカルフルーツのようなおいしさ。
よしっ!ここはひとつ、完熟させねば!と実を一つ、ほったらかしにしていた。
色も明るいオレンジ色になり「そろそろかなー、そろそろかなー」と心待ちにしていたら・・・・・
腐ってしまった(涙)。
種だけは取りおいているので、来年はこの種から苗を育ててみようかな。
なお、下の一皿は、別のゴーヤで作った茄子入りゴーヤチャンプルー。
味付けには味噌を使う。
これは、前出の奄美大島料理のお店で教えていただいた。
奄美大島風のチャンプルーの特徴だとか。
なお、自分で作るときは、種やわたも実ごと輪切りにしてチャンプルーにしている。
種やわたも栄養が豊富らしいので。
そして何よりも、実を縦半分に切り、スプーンで種をかき出して、水でさらして、水分をふきとってって、栄養が逃げていきそうなうえに、め・ん・ど・う。
実ごと炒めると、種のカリカリの触感が、また楽しい。

今年の残暑は、とにかくやる気がありすぎる気がする。
夏バテに効果があると言われるゴーヤ。
さて、お次はどの実をおいしくいただこうかな?
2016年01月31日
寒いこの時季 味噌作り
今年は、寒の入りとともに味噌を仕込んだ。
手前味噌ももう3年目。
発酵食品がマイブームなことは以前にもお伝えした。
「我が家はこうじちゅう-発酵する日常-」はこちら。
ここで「味噌は来年2倍量作る!」と決意表明しており、今年は倍量に挑戦。
その作り方を記事にするが、分量は通常量(今回作った半分)を記載。
まず材料。
大豆 400g
水 適宜
乾燥麹 400g
塩 200g
35度焼酎 適宜
道具は、
ジッパー付ビニール袋大 2枚を2重にして使う
家で一番大きなざる
家で一番大きなボール
家で一番大きな鍋(圧力鍋でも可)
ポテトライサー(あれば)
大豆は、北海道産。これそ有機栽培だのなんだのにすればもっと美味しくなるかもしれないが「万が一」を考えるとそこまで冒険はねぇ。国産が自分なりのレベル維持の限界。
水は、大豆をもどるすのにたっぷりと、大豆をゆでるのにもたっぷり。これも良い水を使えば味もランクアップするかもしれないが、我が家では東京水道水の汲み置き。
麹は、スーパーなどで手に入りやすい乾燥麹。
塩は粗塩!精製塩で作ったことがないから、比べることはできないが、塩自体の味が違うので、ここは粗塩で。
では、作り方。
1.大豆を一晩水に浸す。
大豆は思いのほかふくらむので、たーーーっぷりの水で。
下の方の豆は十分水を吸ったけど、上の方はまだ硬いなんてことのないように。

2.大豆をゆでる。
ざるにあけた大豆を大きな鍋に入れ、かぶるくらいの水をたっぷり注ぎ、強火にかける。煮立ったらふつふつ煮える程度の中火にし、アクを 取りながら4時間ほど、豆が指ではさんで簡単につぶれるほどの柔らからさまで煮る。ゆで汁から豆が頭を出しそうになったら、そのつど水を足す。
と、ここまでは料理本の受け売り。自分は、圧力鍋で弱火からゆっくりと圧をかけ、2時間程度で豆ゆで完了。
ただ、今年は倍量作ったため、さしもの6リットル圧力鍋も吹きこぼれてしまい、えらいことになってしまった。1時間40分で圧力炊きを諦め、豆を確認したら、充分柔らかかったので、これでよしとする。
3.ゆで上がった大豆をざるで煮汁と豆に分ける。どちらも使うよ。
4.大豆は、最大の鍋かボールに入れ、ポテトライサーでつぶす。つぶす。豆の形が残らないようつぶす。ひたすらつぶす。完膚なきまでにつぶす。
ポテトライサーがない場合は、すりこぎでつぶす。フードプロセッサー利用もありかもしれない。
5.これまた大き目のボールに麹をほぐしていれ、3のゆで汁を2カップと混ぜて麹をぱらぱらにほぐす。この時は、焼酎で洗い清めた手でほぐす。乾燥麹は袋を開ける前に、しっかりもみもみしてほぐしておくと胞子が飛び散らなくて扱いやすい。

6.ほぐした麹に塩をいれ、これまた焼酎手でまんべんなく混ぜる。
7.つぶしておいた大豆に、塩と麹を混ぜたもを入れ、こねこねこねこね。
硬すぎてこねにくい場合は、大豆のゆで汁で調整。
ポテトライサー粉砕をかいくぐって形が残っている大豆を発見したら、ここでつぶしておく。

8.そして袋づめ。
重要ポイントは「空気を入れない」。
まず、端っこ角には空気を抜き小さめに丸めたのを詰め、端から空気が入らないようにきちんときちんと詰めていく。
詰め終わったら、袋の口付近に塩を振り、ジッパー部分を焼酎で拭き清める。
9.ビニール袋は、新聞紙などで包み、仕込んだ日付を記入し、涼しく日があたらな場所で保管。
我が家では床下収納でお休みいただいている。
10.時々、ご機嫌伺いし、カビが生えていたら、スプーンで取り除く。
11.1か月後、天地返し。9で仕込み日を記入したのはこのため。意外と忘れてしまうもので。
ここでもカビが生えていたら除去。また、色が違う部分があれば、袋のうえからもみもみ。
袋を開けた場合は、8のように塩を焼酎でお浄め、お浄め。
なお、カメなどに作った時と違い、ビニール袋での天地返しは、楽ちん、楽ちん。
くるっとひっくり返すだけですかからね。
あまりの手軽さに「3回転宙返り」やっちゃたりする。お好みで「ムーンサルト」や「トリプルトゥループ」などでもいいが、最終的に最初の上の面が下になるように。これやらなきゃ、天地返しになりませんから。
12.6か月の熟成を経えて、手前味噌完成!さらに熟成させると美味しさアップ!
熟成した味噌からは液状の味噌たまりがでる。
これは、長芋の拍子木切りを和えたり、豆腐にかけたりに使える調味料。
また、できあがった味噌は、プラスティックの容器に移して使っているが、どんなちまちま移しても、ビニール袋に味噌がくっついている。
このままビニール袋を洗ってしまうにはもったいない。野菜でも漬けておこうかとあれこれ考えていたが、最も単純に対処。
大きめのボールにビニール袋を裏返しにし、水をかけてくっついた味噌を洗い流し、出汁を合わせて味噌汁にしちゃいました。
3人前程度の味噌汁に十分だった。
立春まであと数日の記事アップになってしまったが、最初に作った3年前は寒も終わりはてた3月仕込み。
それでも、充分に美味しかったので、これからお作りになっても大丈夫。
なお、3でとれる大豆のゆで汁。
ゆで汁とあなどることなかれ。これがなかなかの実力者。
これだけで飲んでも「甘~い!」。
今年は、カレーのベースにしたが、味噌汁に煮物にと活用できる。
それから、量り売りでないと、大豆400gはちょっと半端。
300gの袋売りしかない場合は、600gゆでてしまい、オーバー200gのゆでた分見当は別の料理に転用。
今年は、シンプルに五目豆。昨年はつぶしてひき肉と混ぜてハンバーグ。
少し残った豆をそれだけで煮るとまた手間なので、一緒に煮てしまう。
この位、無精して、手抜きしても美味しくできてくれる味噌にありがとう♪
手前味噌ももう3年目。
発酵食品がマイブームなことは以前にもお伝えした。
「我が家はこうじちゅう-発酵する日常-」はこちら。
ここで「味噌は来年2倍量作る!」と決意表明しており、今年は倍量に挑戦。
その作り方を記事にするが、分量は通常量(今回作った半分)を記載。
まず材料。
大豆 400g
水 適宜
乾燥麹 400g
塩 200g
35度焼酎 適宜
道具は、
ジッパー付ビニール袋大 2枚を2重にして使う
家で一番大きなざる
家で一番大きなボール
家で一番大きな鍋(圧力鍋でも可)
ポテトライサー(あれば)
大豆は、北海道産。これそ有機栽培だのなんだのにすればもっと美味しくなるかもしれないが「万が一」を考えるとそこまで冒険はねぇ。国産が自分なりのレベル維持の限界。
水は、大豆をもどるすのにたっぷりと、大豆をゆでるのにもたっぷり。これも良い水を使えば味もランクアップするかもしれないが、我が家では東京水道水の汲み置き。
麹は、スーパーなどで手に入りやすい乾燥麹。
塩は粗塩!精製塩で作ったことがないから、比べることはできないが、塩自体の味が違うので、ここは粗塩で。
では、作り方。
1.大豆を一晩水に浸す。
大豆は思いのほかふくらむので、たーーーっぷりの水で。
下の方の豆は十分水を吸ったけど、上の方はまだ硬いなんてことのないように。

2.大豆をゆでる。
ざるにあけた大豆を大きな鍋に入れ、かぶるくらいの水をたっぷり注ぎ、強火にかける。煮立ったらふつふつ煮える程度の中火にし、アクを 取りながら4時間ほど、豆が指ではさんで簡単につぶれるほどの柔らからさまで煮る。ゆで汁から豆が頭を出しそうになったら、そのつど水を足す。
と、ここまでは料理本の受け売り。自分は、圧力鍋で弱火からゆっくりと圧をかけ、2時間程度で豆ゆで完了。
ただ、今年は倍量作ったため、さしもの6リットル圧力鍋も吹きこぼれてしまい、えらいことになってしまった。1時間40分で圧力炊きを諦め、豆を確認したら、充分柔らかかったので、これでよしとする。
3.ゆで上がった大豆をざるで煮汁と豆に分ける。どちらも使うよ。
4.大豆は、最大の鍋かボールに入れ、ポテトライサーでつぶす。つぶす。豆の形が残らないようつぶす。ひたすらつぶす。完膚なきまでにつぶす。
ポテトライサーがない場合は、すりこぎでつぶす。フードプロセッサー利用もありかもしれない。
5.これまた大き目のボールに麹をほぐしていれ、3のゆで汁を2カップと混ぜて麹をぱらぱらにほぐす。この時は、焼酎で洗い清めた手でほぐす。乾燥麹は袋を開ける前に、しっかりもみもみしてほぐしておくと胞子が飛び散らなくて扱いやすい。

6.ほぐした麹に塩をいれ、これまた焼酎手でまんべんなく混ぜる。
7.つぶしておいた大豆に、塩と麹を混ぜたもを入れ、こねこねこねこね。
硬すぎてこねにくい場合は、大豆のゆで汁で調整。
ポテトライサー粉砕をかいくぐって形が残っている大豆を発見したら、ここでつぶしておく。

8.そして袋づめ。
重要ポイントは「空気を入れない」。
まず、端っこ角には空気を抜き小さめに丸めたのを詰め、端から空気が入らないようにきちんときちんと詰めていく。
詰め終わったら、袋の口付近に塩を振り、ジッパー部分を焼酎で拭き清める。
9.ビニール袋は、新聞紙などで包み、仕込んだ日付を記入し、涼しく日があたらな場所で保管。
我が家では床下収納でお休みいただいている。
10.時々、ご機嫌伺いし、カビが生えていたら、スプーンで取り除く。
11.1か月後、天地返し。9で仕込み日を記入したのはこのため。意外と忘れてしまうもので。
ここでもカビが生えていたら除去。また、色が違う部分があれば、袋のうえからもみもみ。
袋を開けた場合は、8のように塩を焼酎でお浄め、お浄め。
なお、カメなどに作った時と違い、ビニール袋での天地返しは、楽ちん、楽ちん。
くるっとひっくり返すだけですかからね。
あまりの手軽さに「3回転宙返り」やっちゃたりする。お好みで「ムーンサルト」や「トリプルトゥループ」などでもいいが、最終的に最初の上の面が下になるように。これやらなきゃ、天地返しになりませんから。
12.6か月の熟成を経えて、手前味噌完成!さらに熟成させると美味しさアップ!
熟成した味噌からは液状の味噌たまりがでる。
これは、長芋の拍子木切りを和えたり、豆腐にかけたりに使える調味料。
また、できあがった味噌は、プラスティックの容器に移して使っているが、どんなちまちま移しても、ビニール袋に味噌がくっついている。
このままビニール袋を洗ってしまうにはもったいない。野菜でも漬けておこうかとあれこれ考えていたが、最も単純に対処。
大きめのボールにビニール袋を裏返しにし、水をかけてくっついた味噌を洗い流し、出汁を合わせて味噌汁にしちゃいました。
3人前程度の味噌汁に十分だった。
立春まであと数日の記事アップになってしまったが、最初に作った3年前は寒も終わりはてた3月仕込み。
それでも、充分に美味しかったので、これからお作りになっても大丈夫。
なお、3でとれる大豆のゆで汁。
ゆで汁とあなどることなかれ。これがなかなかの実力者。
これだけで飲んでも「甘~い!」。
今年は、カレーのベースにしたが、味噌汁に煮物にと活用できる。
それから、量り売りでないと、大豆400gはちょっと半端。
300gの袋売りしかない場合は、600gゆでてしまい、オーバー200gのゆでた分見当は別の料理に転用。
今年は、シンプルに五目豆。昨年はつぶしてひき肉と混ぜてハンバーグ。
少し残った豆をそれだけで煮るとまた手間なので、一緒に煮てしまう。
この位、無精して、手抜きしても美味しくできてくれる味噌にありがとう♪
2015年12月03日
我が家はこうじちゅう-発酵する日常-
我が家はこうじちゅう。
といっても、家のリフォームを始めたわけではない。
工事ではなく麹なのだ。
ブームからかなり遅れて始めた塩麹。(塩麹と甘酒の記事はこちら)
我が家ではすでにブームを越えて定番調味料。
そして米麹と使った発酵調味料ブームは拡大の一途をたどっている。

写真右上から、反時計回りでご紹介。
右上の茶色のは味噌。一昨年の寒に仕込んだもので、いやいや、香りが良いこと、良いこと。(これがほんとの手前味噌)
味噌は20年以上前に挑戦し、何が悪かったのやらカフカフ状態になり発酵が全く進まず、涙を飲んで廃棄した黒い記憶が。
かなり躊躇したのだが、図書館でお借りした本に密閉ファスナー付きビニール袋で作る方法が書かれており「これなら失敗しても大量じゃないし」と再挑戦。
この味噌、小さな容器に入れて入院中で食事制限のない方にお持ちしたところ「食欲が進んだー!また欲しい」と好評。
来年はチョーシに乗って二倍量を作るつもりでいる。
その左の白っぽいのは、塩麹。
乾燥麹200gに塩120gでかなり塩辛いが、常温保存できる。
その左は、甘酒。
1合のお米を1.5倍の水でゆるめに炊き、それに1合の水を加えて、なんとなく60度位にする。
これにほぐした乾燥麹200gを入れて混ぜる。
あとは、少しふたを開けた炊飯器で保温。
最初は1時間たったらかき混ぜるが、あとは2時間おきにかき混ぜ、10時間程度で甘酒完成。
お米はもち米を使った方がより甘い気がする。
できあがったものは、すぐ食べる分は冷蔵庫で残りは冷凍保存。
その下(下段左端)の赤いのは、コチュジャン。
作り方は「ちょっと硬めに仕立てた甘酒にとうがらしを混ぜる」だけ。
韓国産とうがらしは、国分寺のマルイ地下で購入。
本当は細かいのを入れるところ、勘違いして粗びきを買ってしまった。
それほど辛さに強くはないので、まあよしとする。
炒めもの、鍋の薬味に活躍中。
砂糖+酢+ナンプラー+コチュジャンで、なんとなくスイートチリソース的なものもできる。
これも冷蔵庫保存。
その右の黒っぽいのは醤油麹。
米麹に醤油をひたひたになるまでつけて放置という、この中では最も簡単にできる。
焼く前の肉にもみ込む、生野菜につけて食べるなどして活用中。
これは常温保存している。
その右の白いのは・・・間違えて撮影に入れてしまった、ヨーグルト。
はい、これは麹は使ってません。
低脂肪ヨーグルトと低脂肪牛乳で作ったもの。
低脂肪牛乳を推定60度位に温め、大匙6杯ほどの低脂肪ヨーグルト加えて混ぜ、密閉容器に入れる。
これを、使い古し(でも洗濯済み)のバスタオルでくるみ、発泡スチロールの箱に入れて、一晩。
夕食後におたま一杯分程度を飲んでいるが、これを始めてから、腸の調子が良い気がする。
低脂肪×低脂肪なので、さらさらとして酸味が強い。
たまに普通の牛乳で作るとその濃厚なこと。
毎晩いただくににはちょいと濃すぎる感。
そんなこんなで、乾燥米麹が冷蔵庫に常駐する日々はまだまだ続きそうだ。
といっても、家のリフォームを始めたわけではない。
工事ではなく麹なのだ。
ブームからかなり遅れて始めた塩麹。(塩麹と甘酒の記事はこちら)
我が家ではすでにブームを越えて定番調味料。
そして米麹と使った発酵調味料ブームは拡大の一途をたどっている。

写真右上から、反時計回りでご紹介。
右上の茶色のは味噌。一昨年の寒に仕込んだもので、いやいや、香りが良いこと、良いこと。(これがほんとの手前味噌)
味噌は20年以上前に挑戦し、何が悪かったのやらカフカフ状態になり発酵が全く進まず、涙を飲んで廃棄した黒い記憶が。
かなり躊躇したのだが、図書館でお借りした本に密閉ファスナー付きビニール袋で作る方法が書かれており「これなら失敗しても大量じゃないし」と再挑戦。
この味噌、小さな容器に入れて入院中で食事制限のない方にお持ちしたところ「食欲が進んだー!また欲しい」と好評。
来年はチョーシに乗って二倍量を作るつもりでいる。
その左の白っぽいのは、塩麹。
乾燥麹200gに塩120gでかなり塩辛いが、常温保存できる。
その左は、甘酒。
1合のお米を1.5倍の水でゆるめに炊き、それに1合の水を加えて、なんとなく60度位にする。
これにほぐした乾燥麹200gを入れて混ぜる。
あとは、少しふたを開けた炊飯器で保温。
最初は1時間たったらかき混ぜるが、あとは2時間おきにかき混ぜ、10時間程度で甘酒完成。
お米はもち米を使った方がより甘い気がする。
できあがったものは、すぐ食べる分は冷蔵庫で残りは冷凍保存。
その下(下段左端)の赤いのは、コチュジャン。
作り方は「ちょっと硬めに仕立てた甘酒にとうがらしを混ぜる」だけ。
韓国産とうがらしは、国分寺のマルイ地下で購入。
本当は細かいのを入れるところ、勘違いして粗びきを買ってしまった。
それほど辛さに強くはないので、まあよしとする。
炒めもの、鍋の薬味に活躍中。
砂糖+酢+ナンプラー+コチュジャンで、なんとなくスイートチリソース的なものもできる。
これも冷蔵庫保存。
その右の黒っぽいのは醤油麹。
米麹に醤油をひたひたになるまでつけて放置という、この中では最も簡単にできる。
焼く前の肉にもみ込む、生野菜につけて食べるなどして活用中。
これは常温保存している。
その右の白いのは・・・間違えて撮影に入れてしまった、ヨーグルト。
はい、これは麹は使ってません。
低脂肪ヨーグルトと低脂肪牛乳で作ったもの。
低脂肪牛乳を推定60度位に温め、大匙6杯ほどの低脂肪ヨーグルト加えて混ぜ、密閉容器に入れる。
これを、使い古し(でも洗濯済み)のバスタオルでくるみ、発泡スチロールの箱に入れて、一晩。
夕食後におたま一杯分程度を飲んでいるが、これを始めてから、腸の調子が良い気がする。
低脂肪×低脂肪なので、さらさらとして酸味が強い。
たまに普通の牛乳で作るとその濃厚なこと。
毎晩いただくににはちょいと濃すぎる感。
そんなこんなで、乾燥米麹が冷蔵庫に常駐する日々はまだまだ続きそうだ。
2015年11月13日
奈良の夜のお勧めは 酒肆 華
ちょっと日にちが開いちゃいましたが、11月9日の続き。
風邪のせいか、どうも飲食方面アンテナが立たない今回の奈良の旅。
夜になり、街に繰り出したが、食欲は今一つ。
メインの正倉院展には大満足だったので、二兎を追うのは諦めるか?
幸い、近鉄奈良駅で柿の葉寿司の3個入りを見つけたので、これを購入。
「はあ、もう、宿に戻っちゃおうか」と思い始めたころ「おやおや、これは」と良さげなお店を発見。
人見知りはするが、酒見知りはしない性格ゆえ「一人ですが、よろしいですか?」と入店。
そのお店は、酒肆 華(しゅし はな)さま。

さて、自分、初めてのパン屋さんで購入するのは食パン。
初めてのお蕎麦屋さんで注文するのはもり。
そして、初めてのバーではジンリッキーが定番。
キリッとした味わいが「好み~!」
お次は「甘くしないで」とお願いしてギムレット。

自分はお味に夢中で気づかなかったのだが「このグラスの薄さがいいね」とご指摘になるのは、はやり初めていらしたというお客さま。
初めての方が多いのかと思いきや、徐々に常連客の皆さまで席が埋まっていく。
「そろそろしめの一杯を」とモルトをお願いする。
「どんなモルトがお好みですか?」
「アイラが好きなんですが」
と、お出しいただいたのは自分初めてのCLANDENNY。

数種類のアイラウィスキーと名前を明かせない2か所の蒸留所の原酒がブレンドされたアイラウィスキー。
うまうま。
するとおつまみに出してくださったのが、薄くスライスされた奈良の銘菓柿寿賀。
干し柿を使ったお菓子。
「あう~、あう~」
アシカ化したわけではなく、干し柿の鄙びた味わいと癖のあるアイラが合うのだ。
この柿寿賀、本店が宿の近くだったので「こりゃ、買わねば!」と思ったのだが、開店時間中に行けず無念の断念。
西のスコットランドのウィスキーと、東の奈良のお菓子の調和。
「口の中が正倉院や~!」
こちらのお店で正倉院展情報を教えていただいた。
その内容については11/9の記事に。
詳細はこちらこちら。
ちなみにこの正倉院展の時期は、奈良が最も混雑する時期だそうだ。
他にも、色々と奈良情報を教えていただいた。
出だしは不安材料の多い今回の奈良への旅行。
終わってみれば、結果、とても良きよろしき旅だった。
その掉尾を飾ってくださったのがこの酒肆 華さま。
お店の場所は、三条通りから餅飯殿センター街から一本目の小路を左に入ってすぐ。
餅飯殿は「もちいどの」と読む。

パッと見ると「もいちどの(も一度の)」って読み間違えた。
でも、この読み間違えどおり、も一度おうかがいしたお店だ。
酒肆 華の紹介サイトはこちら。
総本店柿寿賀のサイトはこちら。
第67回正倉院展のサイトはこちら。
2015年07月21日
土用干し始めました おまけ料理情報も
数年前から、断続的に梅を漬けている。
昔ながらのしょっぱい塩対応(?)。荒塩をたっぷり、時期になれば赤紫蘇を揉んで、赤紫に染める梅干しだ。
ただ、厳密に言うと土用干しをしないため、梅漬けなのかもしれない。
30年ほど前、梅を土用干しし、出勤している最中に通り雨に降られ、梅酢で洗い直し、漬けなおすという手間が。それに1kgの梅を干せるような大きな盆もないので、大皿総動員も面倒。
というわけで、「干さなくたっていいじゃないか!」をスローガンにしてしまった。
今年は、1.5kgの熟した梅を購入し、梅ジュース、梅酒、梅干しを500gづつ仕込んだ。
「500gなら、ラップを敷いたお盆の上で干せるなぁ」と思い、梅雨明け十日のこの時期に、梅を干すことに。

そして、早速、昨日は夕方の雨(やれやれ)。
でも、お盆1枚と梅酢の瓶だけなので、撤収作業もすばやく行えた。
今日で2日目。
心なしか梅の色が濃く、香りもたつ。
味にも変化がでるのか、楽しみだ。
そんな梅干し、調味料として使うとなかなか便利。
叩いてペースト状にし、ゆでた肉のたれや、炒めものの調味にお役立ち。
我が家での一番人気は、鶏むね肉をそぎ切りにし、片栗粉かくず粉をまぶしてゆで、冷やしておき、梅干しペーストをつけていただくもの。ひんやりつるりん感覚で、食欲が落ちた時期にもいただきやすい。
これは、15年ほど前に、退院後、ほぼ寝たきり状態だった父のため「高たんぱくで、硬くなくて、さっぱりして、食べやすいもの」と考えて作ったもの。この時は、ささみで作ったっけ。
なお、むね肉の皮をはいで、ゆで汁でゆでせん切りにし、ネギまたは胡瓜のせん切りまたは茄子を蒸して裂くいたのと併せてポン酢で和えると一品追加。
ゆで汁はスープにしたり、寒天を煮溶かして固め、切ってサラダに混ぜても良いお味。
また、ペーストにした梅干しの残った種は、冷蔵庫で冷やしている飲み水に放り込んでおくと、適度に塩分が出て、塩分補給に。ただ、長時間入れておくと、時に、顔がゆがむほどしょっぱかったりする。何事も、過ぎたるは及ばざるがごとし。
暑さも続きそうだが、伝統的食材も活用して、乗り切ろう、この夏。
昔ながらのしょっぱい塩対応(?)。荒塩をたっぷり、時期になれば赤紫蘇を揉んで、赤紫に染める梅干しだ。
ただ、厳密に言うと土用干しをしないため、梅漬けなのかもしれない。
30年ほど前、梅を土用干しし、出勤している最中に通り雨に降られ、梅酢で洗い直し、漬けなおすという手間が。それに1kgの梅を干せるような大きな盆もないので、大皿総動員も面倒。
というわけで、「干さなくたっていいじゃないか!」をスローガンにしてしまった。
今年は、1.5kgの熟した梅を購入し、梅ジュース、梅酒、梅干しを500gづつ仕込んだ。
「500gなら、ラップを敷いたお盆の上で干せるなぁ」と思い、梅雨明け十日のこの時期に、梅を干すことに。

そして、早速、昨日は夕方の雨(やれやれ)。
でも、お盆1枚と梅酢の瓶だけなので、撤収作業もすばやく行えた。
今日で2日目。
心なしか梅の色が濃く、香りもたつ。
味にも変化がでるのか、楽しみだ。
そんな梅干し、調味料として使うとなかなか便利。
叩いてペースト状にし、ゆでた肉のたれや、炒めものの調味にお役立ち。
我が家での一番人気は、鶏むね肉をそぎ切りにし、片栗粉かくず粉をまぶしてゆで、冷やしておき、梅干しペーストをつけていただくもの。ひんやりつるりん感覚で、食欲が落ちた時期にもいただきやすい。
これは、15年ほど前に、退院後、ほぼ寝たきり状態だった父のため「高たんぱくで、硬くなくて、さっぱりして、食べやすいもの」と考えて作ったもの。この時は、ささみで作ったっけ。
なお、むね肉の皮をはいで、ゆで汁でゆでせん切りにし、ネギまたは胡瓜のせん切りまたは茄子を蒸して裂くいたのと併せてポン酢で和えると一品追加。
ゆで汁はスープにしたり、寒天を煮溶かして固め、切ってサラダに混ぜても良いお味。
また、ペーストにした梅干しの残った種は、冷蔵庫で冷やしている飲み水に放り込んでおくと、適度に塩分が出て、塩分補給に。ただ、長時間入れておくと、時に、顔がゆがむほどしょっぱかったりする。何事も、過ぎたるは及ばざるがごとし。
暑さも続きそうだが、伝統的食材も活用して、乗り切ろう、この夏。
2015年05月04日
野菜がとっても高いから 挑戦!茶殻料理
少し、事態は改善されたかに思われるが、例年に比べ、まだまだ野菜が高値。
そこで、以前から気になっていた茶殻料理に本腰を入れてみることにした。
お茶と言えば、紅茶党の自分。
ところが、3年ほど前に扁桃炎で40度の高熱に見舞われた。
この直後から、やたらと緑茶が美味しい。
出る茶殻は、庭木やプランター植物のごはんにしていた。
この緑茶、緑黄色野菜にひけを取らない栄養価ながら、その栄養の7割がお茶を
いれた後の茶殻に残っているとか。
これを、食さないのはもったいない。
先ずは、定番(?)のふりかけ。

めんつゆを作るのに、どっさり使ったいわし節に一緒に使った昆布は細切り。
アクセントに、もどしたきくらげも細切りにしておく。
これに、茶殻も加える。
みりんと砂糖で煮つけ、醤油を加え、なべ底に煮汁が残らなくなる位、具材はしっとり状態で火を止める。
ここで、飽きがこないように、風味を分けてみた。
左は、実山椒入り。右は、刻んだクルミとすりごま入り。
クルミ+すりごまの方が、しっくりくるお味。
実山椒も悪くはないが、この場合、全体の味つけの甘みを控えた方が合いそう。
次は、焼きそば。

具は、しらたき、キャベツ、ちくわ、そして茶殻。
味つけは、和風だし。
三番目は、お好み焼。

薄力粉を、和風だしの素、重曹、そして茶殻を加えた水で溶き、2/3量をフライパンに丸く伸ばす。
その上に、せん切りキャベツ、モヤシ、豚軟骨としらたきの甘辛煮の刻んだの、切りイカを乗せ、しばし焼く。
裏面にほどよい焦げ目がついたところで、上から残りの溶いた粉をかけ、ひっくり返して焼く。
焼きあがったら、ソースと青のりをかける。
豚軟骨としらたきの甘辛煮は、たまたま残り物があったからで、なければ、ちくわでも王道の豚コマでも問題なし。
以上3品ではすべて、三煎まで入れた茶葉を使用。
全く違和感なしで味わえた。
最後に、ケーキ。

これには、すり鉢で細かくし水出茶にした茶殻を使用。
卵2個と豆乳をうーん、1/3カップ位・・・かな?、を溶き混ぜたのに茶殻も混ぜる。
これで、ホットケーキミックス(手抜きデス)を溶き、炊飯器(手抜きデス)に入れ、炊飯ボタンオン。
炊き上がったら、ひっくり返して、再炊飯でできあがり。
ケーキというには、甘さが控えめ。軽食用にはちょうど良い。
自画自賛になるが、どれも普通に美味しくいただける。
しかし、貴重な栄養源に一つを絶たれた、庭やプランターの植物たちが悲しそうな目でこっちを見ている・・・のは、気のせい。
そう、きっと、気のせい。
そこで、以前から気になっていた茶殻料理に本腰を入れてみることにした。
お茶と言えば、紅茶党の自分。
ところが、3年ほど前に扁桃炎で40度の高熱に見舞われた。
この直後から、やたらと緑茶が美味しい。
出る茶殻は、庭木やプランター植物のごはんにしていた。
この緑茶、緑黄色野菜にひけを取らない栄養価ながら、その栄養の7割がお茶を
いれた後の茶殻に残っているとか。
これを、食さないのはもったいない。
先ずは、定番(?)のふりかけ。

めんつゆを作るのに、どっさり使ったいわし節に一緒に使った昆布は細切り。
アクセントに、もどしたきくらげも細切りにしておく。
これに、茶殻も加える。
みりんと砂糖で煮つけ、醤油を加え、なべ底に煮汁が残らなくなる位、具材はしっとり状態で火を止める。
ここで、飽きがこないように、風味を分けてみた。
左は、実山椒入り。右は、刻んだクルミとすりごま入り。
クルミ+すりごまの方が、しっくりくるお味。
実山椒も悪くはないが、この場合、全体の味つけの甘みを控えた方が合いそう。
次は、焼きそば。

具は、しらたき、キャベツ、ちくわ、そして茶殻。
味つけは、和風だし。
三番目は、お好み焼。

薄力粉を、和風だしの素、重曹、そして茶殻を加えた水で溶き、2/3量をフライパンに丸く伸ばす。
その上に、せん切りキャベツ、モヤシ、豚軟骨としらたきの甘辛煮の刻んだの、切りイカを乗せ、しばし焼く。
裏面にほどよい焦げ目がついたところで、上から残りの溶いた粉をかけ、ひっくり返して焼く。
焼きあがったら、ソースと青のりをかける。
豚軟骨としらたきの甘辛煮は、たまたま残り物があったからで、なければ、ちくわでも王道の豚コマでも問題なし。
以上3品ではすべて、三煎まで入れた茶葉を使用。
全く違和感なしで味わえた。
最後に、ケーキ。

これには、すり鉢で細かくし水出茶にした茶殻を使用。
卵2個と豆乳をうーん、1/3カップ位・・・かな?、を溶き混ぜたのに茶殻も混ぜる。
これで、ホットケーキミックス(手抜きデス)を溶き、炊飯器(手抜きデス)に入れ、炊飯ボタンオン。
炊き上がったら、ひっくり返して、再炊飯でできあがり。
ケーキというには、甘さが控えめ。軽食用にはちょうど良い。
自画自賛になるが、どれも普通に美味しくいただける。
しかし、貴重な栄養源に一つを絶たれた、庭やプランターの植物たちが悲しそうな目でこっちを見ている・・・のは、気のせい。
そう、きっと、気のせい。
2015年04月11日
行列のできる蜂楽饅頭
蜂楽饅頭と書いて、何と読む?
正解は「ほうらくまんじゅう」。
福岡市早良区の西新に福岡本店がある、うーん、東京で言う「今川焼」のようなお菓子である。

昔、今は亡き祖父がこの近くの学校で教師をしていたため、時々お土産に買ってきてくれた時の嬉しいこと。
甘い物が苦手な自分でも、大喜びしたのだから、その美味しさをご想像ください。
もっとも、福岡で「今川焼」を見た記憶がなく、類似のお菓子には太閤焼、太鼓焼、七宝焼(!)といった名称のものがあった。
七宝焼は、西鉄平尾駅近くにお店があり、このお店のおかげで、自分、ずーっと七宝焼は食べ物だと思っていた。
東京に出て、先輩が「このブローチ、七宝焼きなの」と言われた時は、びっくり仰天!カルチャーショックだったなぁ。
で、この今川焼系お菓子で、福岡で最も有名なのが、この蜂楽饅頭ではなかろうか?(独断だけど)

天神のデパート岩田屋の地下2階にも売り場があるが、通りかかるといつも行列。
稀に行列がないと「買わなきゃソン!」という気にさえなってくる。
衝動買いしたところで一個100円程度だから、散在には遠く、達成感は大きい。お得だ。
この蜂楽饅頭、ずーっと福岡市は西新発祥のお菓子だと思っていた。
で、今回、記事を投稿するにあたって、ホームページを拝見したところ、あらら、昭和28年に熊本県は水俣市で創業だそうな。
20年以上前に、包装紙に麻布十番支店が印刷されていた気がするが、今、調べたところ、店舗は九州内のみ。
西新のお店にはイートインコーナーがあり、焼き立てをいただける。
持ち帰りの場合でも、トースターなどで、カリッと焼いていただくと、かなり焼き立てに近づく。
なお、この蜂楽饅頭は黒餡と白餡があり、それぞれに熱いファンがいる。
一説によると白餡好きの方がツウだという話も聞くが、自分は黒餡派。
ツウでなくって結構。好み優先上等!
蜂楽饅頭の公式サイトはこちら。
正解は「ほうらくまんじゅう」。
福岡市早良区の西新に福岡本店がある、うーん、東京で言う「今川焼」のようなお菓子である。

昔、今は亡き祖父がこの近くの学校で教師をしていたため、時々お土産に買ってきてくれた時の嬉しいこと。
甘い物が苦手な自分でも、大喜びしたのだから、その美味しさをご想像ください。
もっとも、福岡で「今川焼」を見た記憶がなく、類似のお菓子には太閤焼、太鼓焼、七宝焼(!)といった名称のものがあった。
七宝焼は、西鉄平尾駅近くにお店があり、このお店のおかげで、自分、ずーっと七宝焼は食べ物だと思っていた。
東京に出て、先輩が「このブローチ、七宝焼きなの」と言われた時は、びっくり仰天!カルチャーショックだったなぁ。
で、この今川焼系お菓子で、福岡で最も有名なのが、この蜂楽饅頭ではなかろうか?(独断だけど)

天神のデパート岩田屋の地下2階にも売り場があるが、通りかかるといつも行列。
稀に行列がないと「買わなきゃソン!」という気にさえなってくる。
衝動買いしたところで一個100円程度だから、散在には遠く、達成感は大きい。お得だ。
この蜂楽饅頭、ずーっと福岡市は西新発祥のお菓子だと思っていた。
で、今回、記事を投稿するにあたって、ホームページを拝見したところ、あらら、昭和28年に熊本県は水俣市で創業だそうな。
20年以上前に、包装紙に麻布十番支店が印刷されていた気がするが、今、調べたところ、店舗は九州内のみ。
西新のお店にはイートインコーナーがあり、焼き立てをいただける。
持ち帰りの場合でも、トースターなどで、カリッと焼いていただくと、かなり焼き立てに近づく。
なお、この蜂楽饅頭は黒餡と白餡があり、それぞれに熱いファンがいる。
一説によると白餡好きの方がツウだという話も聞くが、自分は黒餡派。
ツウでなくって結構。好み優先上等!
蜂楽饅頭の公式サイトはこちら。
2015年03月28日
先月のバレンタイン
先月、2月14日の我が家のバレンタインディナー。
今頃の投稿か?投稿か?
いやいや、3年前の金沢旅行の記事に比べれば昨日のことみたいなもんですので(ト、開キナホル)。
前菜は、とりむねハム黒こしょう風味にキノコのガーリックオリーブ漬。これはどちらも作り置き。
スープは、生クリームにほうれん草とブロッコリーの茎とカブの葉のポタージュ風。
生クリームは、ケーキ作りに使ったものの残りを転用。
サラダは、カブ拍子木切、にんじん繊切りにゆでたカブの葉を彩り。しかし、カブの葉は色が変わってしまった。
ドレッシングは、白ワインビネガーに胡椒に自家製レモンの自家製塩レモン。レモンもみじん切りにして混ぜた。ノンオイルにしたので、洋風酢の物っぽい。
そしてメインはローストポーク。豚ロースの固まり肉にフォークでゲシゲシとめったざしにし、塩麹、ハチミツ、ニンニク、胡椒、ローズマリー、セージをこすり付け、置くことしばし。そして、オーブンで焼くのだが、設定時間を過ぎても、生焼け。やらかした!250℃で焼くつもりが、何かを勘違いして180℃の温度設定。夕飯開始時刻、大幅に遅れる。ところが、この予定よりも低めの温度設定がよかったのか、塩麹やハチミツのおかげか、とても柔らかい仕上がり。焼いている途中で、肉の周囲にゆでたじゃがいも、ブロッコリー、コールラビ、かぼちゃをお供に添える。
ローストポークはそのままの味つけでもイケるが、冷凍していた小平産ブルーベリーでソースを作った(あ!写真に入ってないや)。これは、思い切りよく甘目に仕上げることができなかったため、中途半端な味。今後の課題。
パンにはゆで卵と玉ねぎみじん切りをマヨネーズと辛子で合えたディップも用意。

ケーキは、アーモンド粉でしっとりと仕上げたショコラケーキ

このケーキの作り方は、もう30年以上愛読&活用している、マドモアゼルいくこさん著『秘密のダイエットケーキ』で。
卵白の泡立て、生クリームの泡立てが必要で、それぞれの泡立てと卵黄などを混ぜておくのにボールが複数個必要。今回も生クリームの泡立てにはどんぶりを動員。しかし、泡立てはハンドミキサーで楽ちん。
何回も作っているが、まず失敗のないケーキで、お味は抜群。
ローストポーク生焼けで、一時は危ぶまれたバレンタインディナーだったが、おおむね好評で一安心。
で、今回のパン、これは鷹の台の駅近くの麦工房ポム・ド・パンさんで購入。
後日、このお店も、ご紹介いたしましょう。
今頃の投稿か?投稿か?
いやいや、3年前の金沢旅行の記事に比べれば昨日のことみたいなもんですので(ト、開キナホル)。
前菜は、とりむねハム黒こしょう風味にキノコのガーリックオリーブ漬。これはどちらも作り置き。
スープは、生クリームにほうれん草とブロッコリーの茎とカブの葉のポタージュ風。
生クリームは、ケーキ作りに使ったものの残りを転用。
サラダは、カブ拍子木切、にんじん繊切りにゆでたカブの葉を彩り。しかし、カブの葉は色が変わってしまった。
ドレッシングは、白ワインビネガーに胡椒に自家製レモンの自家製塩レモン。レモンもみじん切りにして混ぜた。ノンオイルにしたので、洋風酢の物っぽい。
そしてメインはローストポーク。豚ロースの固まり肉にフォークでゲシゲシとめったざしにし、塩麹、ハチミツ、ニンニク、胡椒、ローズマリー、セージをこすり付け、置くことしばし。そして、オーブンで焼くのだが、設定時間を過ぎても、生焼け。やらかした!250℃で焼くつもりが、何かを勘違いして180℃の温度設定。夕飯開始時刻、大幅に遅れる。ところが、この予定よりも低めの温度設定がよかったのか、塩麹やハチミツのおかげか、とても柔らかい仕上がり。焼いている途中で、肉の周囲にゆでたじゃがいも、ブロッコリー、コールラビ、かぼちゃをお供に添える。
ローストポークはそのままの味つけでもイケるが、冷凍していた小平産ブルーベリーでソースを作った(あ!写真に入ってないや)。これは、思い切りよく甘目に仕上げることができなかったため、中途半端な味。今後の課題。
パンにはゆで卵と玉ねぎみじん切りをマヨネーズと辛子で合えたディップも用意。

ケーキは、アーモンド粉でしっとりと仕上げたショコラケーキ

このケーキの作り方は、もう30年以上愛読&活用している、マドモアゼルいくこさん著『秘密のダイエットケーキ』で。
卵白の泡立て、生クリームの泡立てが必要で、それぞれの泡立てと卵黄などを混ぜておくのにボールが複数個必要。今回も生クリームの泡立てにはどんぶりを動員。しかし、泡立てはハンドミキサーで楽ちん。
何回も作っているが、まず失敗のないケーキで、お味は抜群。
ローストポーク生焼けで、一時は危ぶまれたバレンタインディナーだったが、おおむね好評で一安心。
で、今回のパン、これは鷹の台の駅近くの麦工房ポム・ド・パンさんで購入。
後日、このお店も、ご紹介いたしましょう。
2015年03月04日
雛祭のお膳
さて、昨日、JA東京むさし小平支店の即売会で購入した小平産うど。
これを昨日、雛祭の御膳に加えた。

左のご飯は、鮭ちらし寿司。
寿司飯には、いただき物の鮭カマをゆで、身をほぐしたものと、ゆでた三つ葉の茎を細かく切ったのと、ご飯を炊く時に入れておいた昆布をせん切りにしたのを混ぜた。
きんめの煮つけは、お手製を頂戴したもの。旨い~!あまりに美味しいので、煮汁は後日、おからを炊くのに加えよう。
小皿の下はあさりの佃煮。
雛祭ですからね、貝があった方がよろしいかと、スーパーで買ってきたもの(安易)。
その上の小皿が、自分的メイン。
うどの皮のきんぴら。
ごぼうのきんぴらを作る時は、お砂糖を加えたり、ごま油で炒めたりと風味を加えたりもするが、うどは、うどらしいことが身上。炒めて醤油をじゅっ!とかけただけ。
その右は、皮をむいたうどを粉末かつおだし(てへへ)で煮たのに、カニ缶の葛あんをかけたもの。青みには根っこ部分を切ったのを水耕栽培中の豆苗の新芽。
うどのあく抜きが手抜きだったせいか、若干色が変わってしまったのと、筒切りにしたら、いささか繊維が自己主張。斜めに切ればよかったな、などなど、反省点あり。
そして、お椀は、先週から作っていた粕汁。
白酒の代理って感じで。寿司飯に混ぜた鮭のかまをゆでた汁やカマの身をとった残りの中骨や皮はここに合流している。
全体的に、雅な雛膳というよりも、いささか荒っぽい雛膳。
平安時代から1200年以上、厄を流すにも「この位ガッツがなくっちゃあねぇ」とは、理由にもならない言い訳、言い訳。
しかし、うどの皮のきんぴら、もう半分位になってしまった。
季節のうちに、またうど買いにJA直売所におうかがいするかな?
これを昨日、雛祭の御膳に加えた。

左のご飯は、鮭ちらし寿司。
寿司飯には、いただき物の鮭カマをゆで、身をほぐしたものと、ゆでた三つ葉の茎を細かく切ったのと、ご飯を炊く時に入れておいた昆布をせん切りにしたのを混ぜた。
きんめの煮つけは、お手製を頂戴したもの。旨い~!あまりに美味しいので、煮汁は後日、おからを炊くのに加えよう。
小皿の下はあさりの佃煮。
雛祭ですからね、貝があった方がよろしいかと、スーパーで買ってきたもの(安易)。
その上の小皿が、自分的メイン。
うどの皮のきんぴら。
ごぼうのきんぴらを作る時は、お砂糖を加えたり、ごま油で炒めたりと風味を加えたりもするが、うどは、うどらしいことが身上。炒めて醤油をじゅっ!とかけただけ。
その右は、皮をむいたうどを粉末かつおだし(てへへ)で煮たのに、カニ缶の葛あんをかけたもの。青みには根っこ部分を切ったのを水耕栽培中の豆苗の新芽。
うどのあく抜きが手抜きだったせいか、若干色が変わってしまったのと、筒切りにしたら、いささか繊維が自己主張。斜めに切ればよかったな、などなど、反省点あり。
そして、お椀は、先週から作っていた粕汁。
白酒の代理って感じで。寿司飯に混ぜた鮭のかまをゆでた汁やカマの身をとった残りの中骨や皮はここに合流している。
全体的に、雅な雛膳というよりも、いささか荒っぽい雛膳。
平安時代から1200年以上、厄を流すにも「この位ガッツがなくっちゃあねぇ」とは、理由にもならない言い訳、言い訳。
しかし、うどの皮のきんぴら、もう半分位になってしまった。
季節のうちに、またうど買いにJA直売所におうかがいするかな?
2015年03月03日
江戸のうど
今日は、小平の農協直売所で「うどの即売会」。
朝から寒かったが「春を味わいましょう」とぬくぬく厚着して出かけた。
農協前広場は、うどを購入する方、どちらかへ発送する方、また、すでにうどを積んだ自転車など、うどうどしさにあふれている。

ところで、この江戸東京野菜にも認定されているうど、文化年間(1804年-1818年)に江戸に広まったというから、その伝統は長い。
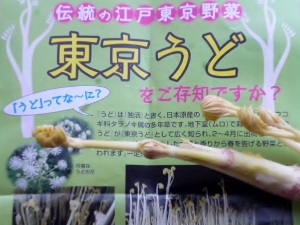
しかし、この時間の投稿では、すでに即売会は終了。
でも、大丈夫。
箱入りのうどは即売日限定だが、バラ売りのうどは、今後も直売所に並ぶとのこと。
歴史あふれるこの春の使者を、膳に載せ、春を感じてみるのもまた一興。
このうども使って、今日の夕餉は雛祭り膳。
献立の詳細は明日にでも。
しかし、今日は寒かった。
うどを買って、農協を出るとパラパラと降ってきたのはあられ。
おやおや、これが本当の「ひなあられ」、なんてな。
朝から寒かったが「春を味わいましょう」とぬくぬく厚着して出かけた。
農協前広場は、うどを購入する方、どちらかへ発送する方、また、すでにうどを積んだ自転車など、うどうどしさにあふれている。

ところで、この江戸東京野菜にも認定されているうど、文化年間(1804年-1818年)に江戸に広まったというから、その伝統は長い。
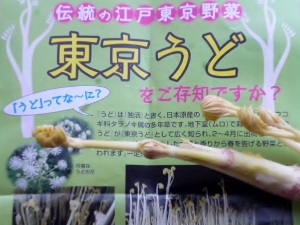
しかし、この時間の投稿では、すでに即売会は終了。
でも、大丈夫。
箱入りのうどは即売日限定だが、バラ売りのうどは、今後も直売所に並ぶとのこと。
歴史あふれるこの春の使者を、膳に載せ、春を感じてみるのもまた一興。
このうども使って、今日の夕餉は雛祭り膳。
献立の詳細は明日にでも。
しかし、今日は寒かった。
うどを買って、農協を出るとパラパラと降ってきたのはあられ。
おやおや、これが本当の「ひなあられ」、なんてな。
2015年01月16日
寒い夜の粕汁
昨日は、寒かった。寒かった。
週間天気予報でも予想されていたので、昨晩に照準を合わせて、粕汁の準備をしていた。

メインは、暮れに頂戴した、岩手県は竹下水産の「寒風干し荒巻鮭」の頭部。(リンク先はいわて三陸復興のかけ橋のページ)

年末に、解体し、すぐに食べない切り身と頭は冷凍庫に。
冷凍庫を開けるたび、口半開きのしゃけと目が合うのは、軽いプレッシャー。
この頭部の更なる解体はまた重労働なので、3日前、そのまま圧力鍋に入れ、ひたひたの水に日本酒と昆布を加え、ゆっくり加熱すること、えーっと、そうだなぁ、多分3時間位?
2日に分けて加圧していたので、正確な時間は不明。
昨日の朝、しゃけ頭に竹串を刺したら、すーっと入る柔らかさ。良きかな、良きかな。
ついでに、干しシイタケを水につけておく。
で、昨日の午後、もう一つの圧力鍋に、干しシイタケの戻し汁を入れ、切ったにんじん、大根、たまねき、じゃがいもを柔らかくする。
そして、柔らかくなった野菜を煮汁ごと、そして、しゃけ頭部を適宜崩しながら、こちらも汁と一緒に普通の鍋に入れる。
しゃけ頭の汁は、かなり塩辛いので、塩梅しながら加える。
そして、残りの具材を入れようとしたら・・・ありゃりゃ、すでに鍋いっぱい。
あと、白菜、しらたき、まいたけ、ごぼう、お揚げを入れようと思っていたのだが、こりゃ、盛りすぎだ。
すでに切っていた白菜はしかたがないので、かさが減ることに期待して入れ、あとの材料は、鍋中のご様子をうかがいながら、ちまちまと追加。
これらに火が通ったところで、粕汁のもう一つのメイン、酒粕。

秋田の銘酒齋彌酒造店 の「雪の茅舎」の酒粕。
袋に「酒がいいから 酒粕もいい」との惹句。
「お豆腐が美味しいお店はおからも美味しい」と思うのだが、これに通じるものがある。
これは、昨年末、国分寺市のOKストアで購入。
冷凍保存していたので、朝のうちに冷凍庫から出して切り分けて深皿に入れておいた。
これに、隠し味程度の味噌を鍋の煮汁とを加え、どろどろどろに溶き、鍋に入れて軽く混ぜ、一煮立ちさせて出来上がり。
今回は写真撮影用に、ゆでたほうれん草を天盛りし、生姜のせん切りを飾ってみたが、そうでなければ、おそらくゆでたほうれん草も、鍋に入れて混ぜ、色は悪く仕上げていたことだろう。でも、その方が味が馴染む気がするもので。
生姜のせん切りもとても合うのだが、へぎ柚子もさわやかで、甲乙つけがたい。
とまれ、おかげで、昨晩の夕食後は、ポカポカだった。
唯一の問題は、まだ残っているしゃけ頭の煮汁。
そうだ、切り干し大根を炊いてみたらどうだろうか?と、先ほど、洗った切り干し大根を水につけてきた。
さあ、どういうお味になりますやら。
週間天気予報でも予想されていたので、昨晩に照準を合わせて、粕汁の準備をしていた。

メインは、暮れに頂戴した、岩手県は竹下水産の「寒風干し荒巻鮭」の頭部。(リンク先はいわて三陸復興のかけ橋のページ)

年末に、解体し、すぐに食べない切り身と頭は冷凍庫に。
冷凍庫を開けるたび、口半開きのしゃけと目が合うのは、軽いプレッシャー。
この頭部の更なる解体はまた重労働なので、3日前、そのまま圧力鍋に入れ、ひたひたの水に日本酒と昆布を加え、ゆっくり加熱すること、えーっと、そうだなぁ、多分3時間位?
2日に分けて加圧していたので、正確な時間は不明。
昨日の朝、しゃけ頭に竹串を刺したら、すーっと入る柔らかさ。良きかな、良きかな。
ついでに、干しシイタケを水につけておく。
で、昨日の午後、もう一つの圧力鍋に、干しシイタケの戻し汁を入れ、切ったにんじん、大根、たまねき、じゃがいもを柔らかくする。
そして、柔らかくなった野菜を煮汁ごと、そして、しゃけ頭部を適宜崩しながら、こちらも汁と一緒に普通の鍋に入れる。
しゃけ頭の汁は、かなり塩辛いので、塩梅しながら加える。
そして、残りの具材を入れようとしたら・・・ありゃりゃ、すでに鍋いっぱい。
あと、白菜、しらたき、まいたけ、ごぼう、お揚げを入れようと思っていたのだが、こりゃ、盛りすぎだ。
すでに切っていた白菜はしかたがないので、かさが減ることに期待して入れ、あとの材料は、鍋中のご様子をうかがいながら、ちまちまと追加。
これらに火が通ったところで、粕汁のもう一つのメイン、酒粕。

秋田の銘酒齋彌酒造店 の「雪の茅舎」の酒粕。
袋に「酒がいいから 酒粕もいい」との惹句。
「お豆腐が美味しいお店はおからも美味しい」と思うのだが、これに通じるものがある。
これは、昨年末、国分寺市のOKストアで購入。
冷凍保存していたので、朝のうちに冷凍庫から出して切り分けて深皿に入れておいた。
これに、隠し味程度の味噌を鍋の煮汁とを加え、どろどろどろに溶き、鍋に入れて軽く混ぜ、一煮立ちさせて出来上がり。
今回は写真撮影用に、ゆでたほうれん草を天盛りし、生姜のせん切りを飾ってみたが、そうでなければ、おそらくゆでたほうれん草も、鍋に入れて混ぜ、色は悪く仕上げていたことだろう。でも、その方が味が馴染む気がするもので。
生姜のせん切りもとても合うのだが、へぎ柚子もさわやかで、甲乙つけがたい。
とまれ、おかげで、昨晩の夕食後は、ポカポカだった。
唯一の問題は、まだ残っているしゃけ頭の煮汁。
そうだ、切り干し大根を炊いてみたらどうだろうか?と、先ほど、洗った切り干し大根を水につけてきた。
さあ、どういうお味になりますやら。
2015年01月03日
今年のおせち
今年のおせちは、暮れに別件で多忙が予想されたので、早く作れるものは早く日持ちしないものはギリギリにと計画したつもりだったが、なんだかバタバタ。

先ずは12/25-27に黒豆。三日がかりと行っても、初日は浸水、中日に圧力鍋で柔らかく煮込み第1回味つけ、千秋楽に更に味を調え後は放置。これが、味つけで砂糖を袋ごと持って、トストスと砂糖を入れていたら、いきなり固まりがドスッ!恐ろしく甘くなってしまったが、家族に言わせると「一般的な黒豆の甘さ」とのこと。
12/25には鯛の昆布締めも。お刺身用のサクに軽く塩をして、昆布で挟み、ラップに包んで冷凍庫へ放り込む。これは当日冷凍庫から出してまだ硬いうちに薄く切り、自然解凍。
同日、鳥ムネ肉を砂糖でもみ、その後塩麹で味付けしたものを冷蔵庫で一晩寝かせ、翌日、ラップで棒状に包み、ゆでてとりハムに。今年は、上にイカ明太を乗せてみた。
12/27からは、おせち作りも本格化。
栗きんとんは、安納芋をおごって、圧力鍋でゆっくり蒸し、皮をむいてつぶしたところに甘栗を混ぜて完了。安納芋が十分に甘いので、お砂糖は入れなかったが、家族からは「甘くないー」とブーイング。甘いよぉーーー。
ごまめ(田作り)は、ここ数年超手抜き。小鍋でしょうゆ風味のカラメルを作り、アーモンドフィッシュとかいうおつまみコーナーで売ってるのを混ぜて、さまして、はい、できあがり。時々カラメル作りに失敗し、デーッと流れてしまう年もあるが、今年は固まってくれている。よかった。
菊花蕪は、小平産小蕪で。
昆布巻きは、毎年、何を巻こうか頭をひねるところ。今年は、ブリ。
そのブリの残りは、焼いて幽庵地に漬ける。単純に塩焼の年もあれば、照り焼きの年もある。
いただきもののカズノコは、塩抜きをして、醤油2、煮切ったみりん1に漬ける。
のしどりは、とりミンチをあたり鉢であたり、卵、小麦粉をつなぎにし、酒、塩、醤油で味付け。
かまぼこは切っただけ。
海老が例年に比べて立ちくらみ起こしそうなほど高値だったので、日の出海老を断念したら、全体的に色合いが地味~。
貴重な彩りになる伊達巻は、12/31の作業。
これは、はんぺんと卵と調味料をバーミキサーで混ぜてフライパンで焼いて、端を切って巻くだけ(今年は、巻く裏表を間違えたみたいだけど)。
作り方は、お手抜きで簡単なのだが、毎回悩むのが味つけ。
甘いのが苦手な自分は、お茶菓子のような味つけの伊達巻は苦手。しかし、家族は甘ーーい伊達巻希望。
折衷味にしようとするために、毎年、半端な伊達巻になる。
今年はその半端さが半端ない状態となり、極端な薄味になってしまった。
やれやれ、来年は腹をくくらにゃなりませんかな。
って、腹のくくりどころが小さいです、自分。
2014年12月25日
イヴイヴディナー
今年は、12月23日のクリスマスイヴイヴにディナー。

チキンは、学園西町の肉の結城屋さまで買ったもも肉。
先週から、塩麹、胡椒、ニンニク、セージ、ローズマリー、オリーブオイルでマリネしていたものをフライパンで焼いたもの。
サラダは、小平産カブ、ロースハム、ゆで卵の白身の賽の目に、今年の夏に買って冷凍しておいたブルーベリーをつぶして混ぜ、塩、こしょう、マヨネーズで味つけ。
これは、確か壇一雄の本で読んだもので、本来は、カブの代わりにゆでたじゃがいも、にんじんの賽の目も入って、ブルーベリーではなくビーツの賽の目でバラ色に染めるサラダ。
ビーツの缶詰を探す暇がなかったため、ブルーベリーで代用。
色は、ビーツを使った時ほど華やかではないものの、落ち着いて侘びだ色合い。
「利休好みサラダ」とでも名付けましょうか。
ただ、ゆでたじゃがいも、にんじんは入れた方が食感がまとまった気がする。
スープは、かぼちゃのポタージュ。
これは12月22日の冬至のかぼちゃを転用。
ゆでかぼちゃをポテトマッシャーでつぶし、牛乳でのばし、塩胡椒で味つけ。
パンは、以前こちらでご紹介した、ブーランジェリー ア プッチ ヴーさまのミニバゲット。
パン用のスプレッドは、刻んだゆで卵のマヨネーズあえ、クリームチーズに刻んだドライフルーツと少し蜂蜜を加えたものに、同じクリームチーズに黒胡椒の挽いたのを混ぜたもの。
そして、寒気がするので、赤ワインにシナモン、クローヴ、ナツメグ(いずれもパウダー)を加えて温めたグリューヴァイン。
今年は、あれやこれやと慌ただしくしていたため、ずいぶん手抜き、思いつきになったが、そこそこイケるディナーだったと自画自賛。
グリューヴァインのおかげか、寒気は治まり、風邪もひかず今日に至っている。

チキンは、学園西町の肉の結城屋さまで買ったもも肉。
先週から、塩麹、胡椒、ニンニク、セージ、ローズマリー、オリーブオイルでマリネしていたものをフライパンで焼いたもの。
サラダは、小平産カブ、ロースハム、ゆで卵の白身の賽の目に、今年の夏に買って冷凍しておいたブルーベリーをつぶして混ぜ、塩、こしょう、マヨネーズで味つけ。
これは、確か壇一雄の本で読んだもので、本来は、カブの代わりにゆでたじゃがいも、にんじんの賽の目も入って、ブルーベリーではなくビーツの賽の目でバラ色に染めるサラダ。
ビーツの缶詰を探す暇がなかったため、ブルーベリーで代用。
色は、ビーツを使った時ほど華やかではないものの、落ち着いて侘びだ色合い。
「利休好みサラダ」とでも名付けましょうか。
ただ、ゆでたじゃがいも、にんじんは入れた方が食感がまとまった気がする。
スープは、かぼちゃのポタージュ。
これは12月22日の冬至のかぼちゃを転用。
ゆでかぼちゃをポテトマッシャーでつぶし、牛乳でのばし、塩胡椒で味つけ。
パンは、以前こちらでご紹介した、ブーランジェリー ア プッチ ヴーさまのミニバゲット。
パン用のスプレッドは、刻んだゆで卵のマヨネーズあえ、クリームチーズに刻んだドライフルーツと少し蜂蜜を加えたものに、同じクリームチーズに黒胡椒の挽いたのを混ぜたもの。
そして、寒気がするので、赤ワインにシナモン、クローヴ、ナツメグ(いずれもパウダー)を加えて温めたグリューヴァイン。
今年は、あれやこれやと慌ただしくしていたため、ずいぶん手抜き、思いつきになったが、そこそこイケるディナーだったと自画自賛。
グリューヴァインのおかげか、寒気は治まり、風邪もひかず今日に至っている。
2014年10月19日
食べるか?飲むか?「ごはん家椒房庵」
博多駅のレストランフロアくうてんにごはん家椒房庵がある。
椒房庵は、もともと創業100年以上の老舗醤油屋。こちらが、博名物辛子明太子を生産販売を始めたのが1989年。1960年が現在の形の辛子明太子の始まりといわれる業界では、やや後発なのかもしれない。
しかし、調味料のプロの技を活かした!と思われる味の良さ、やほどの良いバリエーションでここ10年以上、愛好している。
この椒房庵が満を持して(根拠はありませんが)、飲食店舗出店1号店がここごはん家椒房庵。
さて、あれこれ言うより、いただきましょう、いただきましょう。
珍味盛り合わせ。

上から時計回りに、明太子、イカ明太、イカゆず麹漬。
日本酒によし、ごはんによし。
どれもお店や空港の売店で購入できる。

日本酒。実は、ここの写真、3年前に行った時のもの、銘柄すでに忘却(申し訳ない)。
でも、旨かった!ことは覚えている。

つくねには卵の黄身をからめて。

土鍋炊きのごはん。
ちょっとお時間がかかるので、お早目の注文が望ましい。
このお店の難点は、人気があってなかなか入れないこと!
3年前に入れたのも、17時からの夜時間始まりと同時に入店したからだ。
その後、去年、今年とランチ時におうかがいしたが、どちらも待ち人多しで断念。
そして、タイトルの食べるか?飲むか?
白いご飯に合うおかずって、日本酒にも合うんだなぁ。
だから、夜ならば、食べて、飲むのが正解でしょう。
今回も前回に続き、仕込み記事です。
2014年10月12日
博多のうどん 因幡うどん
博多といえばラーメンが有名だが、博多うどんもなかなかのもの。
それぞれにお好みのお店があるかと思うが、自分のおすすめは因幡うどん さま。
お店の前を通るだけで、馥郁たる出汁の香りに抗うことは難しい。
こちらをおすすめする理由は、お味が良いのはもちろんだが、お店が福岡市の繁華街の天神、博多駅、そしてビジネス街の渡辺通というアクセスの良いところにあるからでもある。
出張で「博多らしいもの食べたいけど、時間がー!」という方も、ご利用しやすいのではないかと。
おすすめのおうどんは、下の写真にある丸天うどん。

福岡では、いわゆる天ぷらもさつま揚げも天ぷらという。
あえて区別をつけるならば、さつま揚げは天ぷらかまぼこと呼ぶ。
丸い天ぷらかまぼこが載っているので、丸天うどんというわけ。
他におすすめは、ごぼ天うどん(ごぼうのかき揚げのっけ)や
こぶうどん(とろろこぶのっけ)。
そして、ネギは、青ねぎ!
キツネ色のつゆに、柔らかいのにコシがある麺の白にお好みの具。
その上に輝くは、緑色のねぎ。
これが、博多うどんの王道!って、ちょっと大げさですが。

東京に住んでいると、なかなかこの味に出会えない。
数年前に帰省し、高校時代の友人と会った時のこと。
「何食べたい?」と聞かれたので「おうどん!」と答えた。
も少しオシャレなものを予定していたらしい彼女は「え?うどん?」と、困惑顔。
「東京じゃ、うどんを食べられんっちゃもん」とゴリ押し。
彼女は、親切に一緒にうどんに付き合ってくれた。
東京に戻って数日後、彼女から小包が届いた。
中身はうどんの乾麺。
添えられた手紙には「うどんも食べられない生活と聞いて心配してます」
わー!言葉、足りなかったー!
心配かけてごめん。あの時のうどん、ありがとね。
因幡うどんの詳細はこちら。
なお、現在、帰省中。ブログ更新ができないので、帰省前に仕込んでおいた記事です。
それぞれにお好みのお店があるかと思うが、自分のおすすめは因幡うどん さま。
お店の前を通るだけで、馥郁たる出汁の香りに抗うことは難しい。
こちらをおすすめする理由は、お味が良いのはもちろんだが、お店が福岡市の繁華街の天神、博多駅、そしてビジネス街の渡辺通というアクセスの良いところにあるからでもある。
出張で「博多らしいもの食べたいけど、時間がー!」という方も、ご利用しやすいのではないかと。
おすすめのおうどんは、下の写真にある丸天うどん。

福岡では、いわゆる天ぷらもさつま揚げも天ぷらという。
あえて区別をつけるならば、さつま揚げは天ぷらかまぼこと呼ぶ。
丸い天ぷらかまぼこが載っているので、丸天うどんというわけ。
他におすすめは、ごぼ天うどん(ごぼうのかき揚げのっけ)や
こぶうどん(とろろこぶのっけ)。
そして、ネギは、青ねぎ!
キツネ色のつゆに、柔らかいのにコシがある麺の白にお好みの具。
その上に輝くは、緑色のねぎ。
これが、博多うどんの王道!って、ちょっと大げさですが。

東京に住んでいると、なかなかこの味に出会えない。
数年前に帰省し、高校時代の友人と会った時のこと。
「何食べたい?」と聞かれたので「おうどん!」と答えた。
も少しオシャレなものを予定していたらしい彼女は「え?うどん?」と、困惑顔。
「東京じゃ、うどんを食べられんっちゃもん」とゴリ押し。
彼女は、親切に一緒にうどんに付き合ってくれた。
東京に戻って数日後、彼女から小包が届いた。
中身はうどんの乾麺。
添えられた手紙には「うどんも食べられない生活と聞いて心配してます」
わー!言葉、足りなかったー!
心配かけてごめん。あの時のうどん、ありがとね。
因幡うどんの詳細はこちら。
なお、現在、帰省中。ブログ更新ができないので、帰省前に仕込んでおいた記事です。
2014年05月31日
ノビル顛末
5月10日に収穫したノビル。
当日の夕食として、無事に食した。

メインのとりてんの左が、桜エビとノビルの葉と根のかきあげ。
味は悪くなかったが、葉っぱ、かなり筋こばっていた。
葉っぱを食べるにゃ、もっと早い時期がよかったのかも。
上中央が、ノビルの鱗茎をさっと湯がいたもの。
自分は、酢味噌よりただの味噌をつけていただく方が、キリッとして断然好みだったが、家族は酢味噌の方がいいとのこと。
これは、各人のお好み。
今現在、ノビルの葉は枯れてしまっている。
「来年も楽しみにしてるよー」と舌なめずりしながら応援する自分。
身勝手極まりない話だが、仕方がない。
これも生きていくということの、一面なのだから。
当日の夕食として、無事に食した。

メインのとりてんの左が、桜エビとノビルの葉と根のかきあげ。
味は悪くなかったが、葉っぱ、かなり筋こばっていた。
葉っぱを食べるにゃ、もっと早い時期がよかったのかも。
上中央が、ノビルの鱗茎をさっと湯がいたもの。
自分は、酢味噌よりただの味噌をつけていただく方が、キリッとして断然好みだったが、家族は酢味噌の方がいいとのこと。
これは、各人のお好み。
今現在、ノビルの葉は枯れてしまっている。
「来年も楽しみにしてるよー」と舌なめずりしながら応援する自分。
身勝手極まりない話だが、仕方がない。
これも生きていくということの、一面なのだから。
2014年05月10日
八年目のノビル
我が家の庭は、非常にわかりやすい。
食べられる植物→自分が植栽
それ以外の植物→家族または前住民が植栽
そんな自分が植栽した植物の一つが野蒜(ノビル)。
以前の派遣先の庭で『雑草』とされていたのを、一部を持ち帰り、庭に植えた。
それから、3年ほどしてそっと掘り起こしてみるたが、まだまだヒヨヒヨとして食べられる状態ではなかったのでまた埋め戻し。
葉っぱは時々、ネギやニラ代わりに使っていたが、掘り起こすのは遠慮していた。
正直「普通に庭に植えられたら、根(鱗茎)を太らせる必要もないのかなー」などと、諦めムードだった。
そして、今朝、雑草を抜いていたら一緒に白くて丸っこいのが抜けた。
「わー!ノビルだー!」
さっそく、茎の太いのを選んで抜いてみると、コロコロと可愛いのが出てくる出てくる。
今日のところはとりあえず8本抜いて、今は泥落としのため水につけてある。

さあ、今夜はなににしよう。
さっとゆでて酢味噌でいただくか、ちょっとがんばって天ぷらにしてみるか。
思えば、庭に移植してから8年。
言ってみれば「桃栗三年ノビル八年」。
「時間をかけて育てれば、得るものがあるものだなぁ」と感慨にふけるも、
「『育てる』って、あんたなんもしてないでしょうがー」とノビルの合唱が聞こえる。
そうだね、庭に植えた後は、特に世話らしいことはなにもやってない。
うんうん、ありがと、ノビル。あんたは偉い!
時に、明日は小平市立中央公園で第22回こだいらグリーンフェスティバルが開催される。
野菜や苗の販売やカブトムシの幼虫、食物資源堆肥の無料配布。
ステージではブーケづくりデモンストレーションや草笛演奏、ダンスなどなど。
そうそう、コダレンジャー、ぶるべーに加えて、今年はクロコダイラも登場するそうな。
去年買った、ミントとパセリの苗は、今も育っている。
明日はお天気にも恵まれそう。
さて、今年は何の苗を買おうかなー。
食べられる植物→自分が植栽
それ以外の植物→家族または前住民が植栽
そんな自分が植栽した植物の一つが野蒜(ノビル)。
以前の派遣先の庭で『雑草』とされていたのを、一部を持ち帰り、庭に植えた。
それから、3年ほどしてそっと掘り起こしてみるたが、まだまだヒヨヒヨとして食べられる状態ではなかったのでまた埋め戻し。
葉っぱは時々、ネギやニラ代わりに使っていたが、掘り起こすのは遠慮していた。
正直「普通に庭に植えられたら、根(鱗茎)を太らせる必要もないのかなー」などと、諦めムードだった。
そして、今朝、雑草を抜いていたら一緒に白くて丸っこいのが抜けた。
「わー!ノビルだー!」
さっそく、茎の太いのを選んで抜いてみると、コロコロと可愛いのが出てくる出てくる。
今日のところはとりあえず8本抜いて、今は泥落としのため水につけてある。

さあ、今夜はなににしよう。
さっとゆでて酢味噌でいただくか、ちょっとがんばって天ぷらにしてみるか。
思えば、庭に移植してから8年。
言ってみれば「桃栗三年ノビル八年」。
「時間をかけて育てれば、得るものがあるものだなぁ」と感慨にふけるも、
「『育てる』って、あんたなんもしてないでしょうがー」とノビルの合唱が聞こえる。
そうだね、庭に植えた後は、特に世話らしいことはなにもやってない。
うんうん、ありがと、ノビル。あんたは偉い!
時に、明日は小平市立中央公園で第22回こだいらグリーンフェスティバルが開催される。
野菜や苗の販売やカブトムシの幼虫、食物資源堆肥の無料配布。
ステージではブーケづくりデモンストレーションや草笛演奏、ダンスなどなど。
そうそう、コダレンジャー、ぶるべーに加えて、今年はクロコダイラも登場するそうな。
去年買った、ミントとパセリの苗は、今も育っている。
明日はお天気にも恵まれそう。
さて、今年は何の苗を買おうかなー。
2013年07月03日
富士の麓の鹿カレー 松風
昨日の記事の続き。
桜、富士山を堪能した後、お昼に入ったお店が本栖湖湖畔にある松風さま。
ガイドブックを見ていて「シカ料理」に興味を持ったから。
こちらのマスターは、なんと猟師で、出される鹿や猪はすべて、ご自身で
捕らえ、加工なさったものだとか。
「地産地消」ならぬ「地猟地消」。

鹿カレーセットには、鹿のたたきや竜田揚げ、鹿や猪の燻製と、口中ジビエ
の旨さでいっぱい。


鹿肉は、高たんぱく、低カロリー、低脂肪、低コレステロールで消化良し、
と身体によさそう。
猪肉も、低カロリー、低脂肪、疲労回復や代謝を促すビタミンB群が豊富
だとか。
最近、野生動物が増えて、農作物に被害が出たり、住宅地にまで出没し
けが人が出たりというニュースをTVで見聞きする。
人間が野や山を開発しておいて、行き場を失った野生動物に対し「害獣
による被害」というのも、手前勝手が気もする。
「害獣、害獣」と困りもの扱いするよりも、食材として美味しくいただいちゃう
のは、どうだろう。
動物にしてみれば「害獣」も「食材」もいい迷惑だろうが、そこはお互い「何
かを食べなきゃ生きていけない生き物」。
美味しくいただきながら、共存共栄の道を模索できればと思う・・・などと書
いてみるが、また食べたい感が満載の記事だな、こりゃ。
桜、富士山を堪能した後、お昼に入ったお店が本栖湖湖畔にある松風さま。
ガイドブックを見ていて「シカ料理」に興味を持ったから。
こちらのマスターは、なんと猟師で、出される鹿や猪はすべて、ご自身で
捕らえ、加工なさったものだとか。
「地産地消」ならぬ「地猟地消」。

鹿カレーセットには、鹿のたたきや竜田揚げ、鹿や猪の燻製と、口中ジビエ
の旨さでいっぱい。


鹿肉は、高たんぱく、低カロリー、低脂肪、低コレステロールで消化良し、
と身体によさそう。
猪肉も、低カロリー、低脂肪、疲労回復や代謝を促すビタミンB群が豊富
だとか。
最近、野生動物が増えて、農作物に被害が出たり、住宅地にまで出没し
けが人が出たりというニュースをTVで見聞きする。
人間が野や山を開発しておいて、行き場を失った野生動物に対し「害獣
による被害」というのも、手前勝手が気もする。
「害獣、害獣」と困りもの扱いするよりも、食材として美味しくいただいちゃう
のは、どうだろう。
動物にしてみれば「害獣」も「食材」もいい迷惑だろうが、そこはお互い「何
かを食べなきゃ生きていけない生き物」。
美味しくいただきながら、共存共栄の道を模索できればと思う・・・などと書
いてみるが、また食べたい感が満載の記事だな、こりゃ。
2013年06月16日
ぬか漬けはじめました
おいしい夏野菜が楽しみになるこれからの季節。
これに向けて、ぬかどこを作った。
前回作っていたものが、入院手術で放置していたため、カビこそ生えては
いなかったものの、なんとも「マズ~~~イ」ものになってしまったため、
新規まき直し。
材料はこちら。

ぬか、とうがらし、しょうが、昆布、そして山椒の実。
今年は、庭の山椒の実が豊作だったので、贅沢に混ぜ込んでみた。
なかなか香りが良い。
普通は、1週間ほど捨て漬けをするというが、それも野菜だ。
うちではこれも食べちゃってる。
そのままでもいいし、野菜炒めに混ぜてもいい。
ぬかどこは、大きめの密閉容器に入れ、冷蔵庫で管理。
いささかつかりは遅いが、傷みの心配がない。
今月初め、高熱で全く手入れができなかったが、冷蔵庫インのおかげで
ぬかどこは無事だった。
さて、そんなぬかどこのメインは何と言ってもぬか。
これは、小川東町の丸山幼稚園のお向かいにあるコーラ米店さまで。
小川東町に住んでいた時も、こちらのぬかを使っていたが、香り、手触りが抜群!
こちらのぬかをつかったら、申し訳ないがスーパーのぬかは・・・。
きゅうりに茄子に大根に、そうそう、大根の葉っぱのぬか漬けも美味。
これで、夏野菜が一層楽しみな今日この頃である。
これに向けて、ぬかどこを作った。
前回作っていたものが、入院手術で放置していたため、カビこそ生えては
いなかったものの、なんとも「マズ~~~イ」ものになってしまったため、
新規まき直し。
材料はこちら。

ぬか、とうがらし、しょうが、昆布、そして山椒の実。
今年は、庭の山椒の実が豊作だったので、贅沢に混ぜ込んでみた。
なかなか香りが良い。
普通は、1週間ほど捨て漬けをするというが、それも野菜だ。
うちではこれも食べちゃってる。
そのままでもいいし、野菜炒めに混ぜてもいい。
ぬかどこは、大きめの密閉容器に入れ、冷蔵庫で管理。
いささかつかりは遅いが、傷みの心配がない。
今月初め、高熱で全く手入れができなかったが、冷蔵庫インのおかげで
ぬかどこは無事だった。
さて、そんなぬかどこのメインは何と言ってもぬか。
これは、小川東町の丸山幼稚園のお向かいにあるコーラ米店さまで。
小川東町に住んでいた時も、こちらのぬかを使っていたが、香り、手触りが抜群!
こちらのぬかをつかったら、申し訳ないがスーパーのぬかは・・・。
きゅうりに茄子に大根に、そうそう、大根の葉っぱのぬか漬けも美味。
これで、夏野菜が一層楽しみな今日この頃である。
2013年01月22日
米と麹と甘い生活
昨年11月「ひともすなる塩麹といふものを、我もしてみんとて」塩麹を作ってみた。
だいたい、流行っている時は、材料(今回は麹)の売切れ状態が続くので、終息した頃に手をだすため、ノリも話題性も遅くなる。
しかし、我が家に遅れてきた塩麹。
これが、なかなか良かった。
肉にもみこんで料理すると、肉は旨いし柔らかい。
で、次は甘酒にチャレンジしようと、昨年から麹を買い、備えていた。
昨日の天気予報では、今日は雨か雪。ちょうど自宅作業の仕事もあるので、一日在宅甘酒製造日にした。
というのも、甘酒は2,3時間おきに混ぜるので、家にいる日に作るのがちょうどよさそう。
また、炊飯器の保温機能を10時間スイッチいれっぱなしなので、寒い日の暖房プラスアルファにもなりそうだし。
5時間ほどで混ぜるついでにちょっとお味見。
「甘~い!」
もうこれでいいんじゃないかとも思ったが、甘酒初心者としては、ここは作り方に従順であろう。
その後、混ぜるたびに味見をすると、そのたびに甘さが濃く深くなっていく。
勝手な判断しなくてよかった、初心者。
できあがりを熱いうちに。

素朴な甘さと懐かしい風味♪
かなり水分少な目な分量で作ってみたので、熱いお湯に混ぜていただくと、かなり暖まりそう。
定番のショウガ汁を混ぜるのもいいな。
おかゆを炊くのと温度管理がめんどうかもしれないが、ここは炊飯器の機能に全面協力を仰いだので「楽させてもらって美味しいのできた」のお得感。
「あー、充実の一日だったー」って、あれ?
仕事は?
仕事・・・
仕事、まだ終わってないよー!
だいたい、流行っている時は、材料(今回は麹)の売切れ状態が続くので、終息した頃に手をだすため、ノリも話題性も遅くなる。
しかし、我が家に遅れてきた塩麹。
これが、なかなか良かった。
肉にもみこんで料理すると、肉は旨いし柔らかい。
で、次は甘酒にチャレンジしようと、昨年から麹を買い、備えていた。
昨日の天気予報では、今日は雨か雪。ちょうど自宅作業の仕事もあるので、一日在宅甘酒製造日にした。
というのも、甘酒は2,3時間おきに混ぜるので、家にいる日に作るのがちょうどよさそう。
また、炊飯器の保温機能を10時間スイッチいれっぱなしなので、寒い日の暖房プラスアルファにもなりそうだし。
5時間ほどで混ぜるついでにちょっとお味見。
「甘~い!」
もうこれでいいんじゃないかとも思ったが、甘酒初心者としては、ここは作り方に従順であろう。
その後、混ぜるたびに味見をすると、そのたびに甘さが濃く深くなっていく。
勝手な判断しなくてよかった、初心者。
できあがりを熱いうちに。

素朴な甘さと懐かしい風味♪
かなり水分少な目な分量で作ってみたので、熱いお湯に混ぜていただくと、かなり暖まりそう。
定番のショウガ汁を混ぜるのもいいな。
おかゆを炊くのと温度管理がめんどうかもしれないが、ここは炊飯器の機能に全面協力を仰いだので「楽させてもらって美味しいのできた」のお得感。
「あー、充実の一日だったー」って、あれ?
仕事は?
仕事・・・
仕事、まだ終わってないよー!














